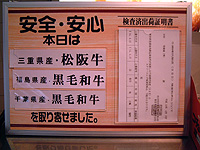| 成長するカテゴリーキラーの真実「選ばれし、食肉専門店」 | |
|---|---|
| 「食肉カテゴリーキラーの出現」 | |
|
|
|
| 「昭和52年 直方 食肉ビックリ市開催」 | |
昭和52年に福岡県直方市で開催された「明治屋産業株式会社」が全国の「週末ビックリ市」ブームを起こす火付け役と なった。 なった。当時の本社敷地内で始めて開催された「食肉びっくり市」は2万坪の広大な敷地の中で開催され、1日に2万人の入場者があった。 現在は、遊戯施設も設け開催され、多くのテナントが軒をならべる大バザールへと変身している。 明治屋産業の「びっくり市」の魅力は、「肉が安く買えること」にあるが、大量仕入れ・大量販売による安さばかりでなく、大型冷凍・冷蔵庫を活用し同じ品質の肉を品切れをおこさずに提供する事で、消費者の信頼をつかんだ事にある。 食肉のバイイングパワーで、同社は冷凍輸入牛肉の販売店から、総合食肉提案タイプのショップである「BIG BIG」での形態での出店に力を入れていく事になる。 現在北海道から札幌まで150店舗を展開し、年商は500億円に達している。(グループで210店舗) 現在の、直方の「食肉びっくり市」には、ワンウエイ導線の精肉・食肉加工肉に続いてミールソリューションに答える157尺の「キッチンスタジオびっくり工房」が新設され現在も週末の3日間で6万人の集客を誇っている。 明治屋産業の成功は各地に、「肉のビックリ市」ブームを作ったが、各地に氾濫した、週末市場は、次第に地域1番店の「肉のびっくり市」に集約されていく。 |
|
| 「各地で肉のびっくり市が成長」 | |
 「カウボーイ」(本社 札幌市)の店作りは「まち作り」といえるものである。 「カウボーイ」(本社 札幌市)の店作りは「まち作り」といえるものである。昭和54年に本社と加工工場を東区伏古に新設し、そこで「土日ショッピングセンター」を開設した。 従来の生鮮の青果・鮮魚・精肉をそれぞれ、150坪(当時1973年施行「大店法」の出店規制の範囲内)の独立した建物を「まち」に集合させ、「雑貨」・「酒」・「レストラン」(食べ放題バイキング)を加え、バザール的な演出と、テナントの集合による専門店の「プロ化」をはかった。 さらに、周辺の開発によってロードサイドに異業種の郊外型店舗を集結させることによる相乗効果を発揮させ、集客力のアップをみせている。 したがって「カウボーイ」の商圏範囲は広く、当時は25キロ圏内を想定しての出店であった。 その後本州にも出店し、1994年5月にジャスダックに株式公開をし、7月「上越ウィング」を開設することになり、デベロッパー事業に本格的に参入する事になった。 愛知県小牧市に本社のある「三河屋」は昭和56年10月に開設された。 牛肉自由化当時は、土・日の2日間で客数1万2千、客単価1万2千円を上げていた。 三河屋は、肉のカテゴリーごとに販売強化の重点を置き、分業化・プロ化による商品と売り場を形成し、細かいMD政策を掲げ、売り場は狭いが深くプロ化を目指した超繁盛店であった。 現在は、小牧市にあったウィークリー市場は「ビッグリブ食品館」の名称に代わり、カーマ・ユニクロ・ヘルスバンクなどのテナントショップが出店している「小牧パワーセンター」に変身している。 他に安城・可児市などに「ビッグリブ食品館」を出店し、肉を中心とした総合食品のカテゴリーキラーに成長している。 |
|
| 「カテゴリーキラーの新業態」 | |
|
専門店の個性的な店作りでたえず新風を吹き入れてくれるのが「ダイリキ」(本社 大阪市)である。 |
|
| 「各地のカテゴリーキラーが地域を越え競合へ」 | |
| 各地で成長していた食肉カテゴリーキラーも地域を越えて競合する時代がやってきた。 80年代後半に起こった首都圏での百貨店テナントとしての生鮮カテゴリーキラー誘致がそれである。 精肉のテナントとして1988年川崎駅前の西武に「BIG BIG」の店名で「明治屋産業」が出店し、関東のカテゴリーキラーと競合する事になる。 「ニュークイック」は、首都圏を中心に駅ビル、百貨店などを中心に出店しており、川崎駅ビル「BE」と川崎モアーズに出店していた。また、JRで駅1つ北の蒲田駅・南の鶴見駅のソレゾレの駅ビルに出店しており壮絶な価格戦争が起こった。 チラシ価格が何でも100g10円から、という時期もあった。 明確な価格差での量販にスーパーマーケットや他の商業集積の店舗は価格に度肝を抜かれた時代であった。 首都圏のカテゴリーキラー対策でイトーヨーカ堂が89年11月29日に基幹店舗の船橋店に大阪のダイリキの「オールデイズ」を対面のコンセとして導入し、カテゴリーキラーのノウハウ吸収を始めた。それがヨーカドーの直営生鮮カテゴリーの「エブリデイ」へと進化していく。 大型商業集積は、集客力のあるテナントとして、マイカル・ユニー・イズミヤなどの大型GMSはコンセとしてカテゴリーキラーを取り込み、精肉部全体としての強化に方向を転換していった。 この時期、1990年以降、バブルの崩壊後の消費低迷と、90年台初頭の大型店舗の積極出店があいまってカテゴリーキラーの出店要請が激増し、その売上規模は拡大し、出店は加速していく。 そして、 駅ビルや駅前百貨店、ビッグチェーンの大型店やショッピングセンターのテナントとして集客に貢献していくのである。 |
|
| 「さらにカテゴリーキラーの活躍の場が広がる」 | |
 各地で成長していた食肉カテゴリーキラーも地域を越えて競合する時代がやってきた。 各地で成長していた食肉カテゴリーキラーも地域を越えて競合する時代がやってきた。80年代後半に起こった首都圏での百貨店テナントとしての生鮮カテゴリーキラー誘致がそれである。 精肉のテナントとして1988年川崎駅前の西武に「BIG BIG」の店名で「明治屋産業」が出店し、関東のカテゴリーキラーと競合する事になる。 「ニュークイック」は、首都圏を中心に駅ビル、百貨店などを中心に出店しており、川崎駅ビル「BE」と川崎モアーズに出店していた。また、JRで駅1つ北の蒲田駅・南の鶴見駅のソレゾレの駅ビルに出店しており壮絶な価格戦争が起こった。 チラシ価格が何でも100g10円から、という時期もあった。 明確な価格差での量販にスーパーマーケットや他の商業集積の店舗は価格に度肝を抜かれた時代であった。 首都圏のカテゴリーキラー対策でイトーヨーカ堂が89年11月29日に基幹店舗の船橋店に大阪のダイリキの「オールデイズ」を対面のコンセとして導入し、カテゴリーキラーのノウハウ吸収を始めた。それがヨーカドーの直営生鮮カテゴリーの「エブリデイ」へと進化していく。 大型商業集積は、集客力のあるテナントとして、マイカル・ユニー・イズミヤなどの大型GMSはコンセとしてカテゴリーキラーを取り込み、精肉部全体としての強化に方向を転換していった。 この時期、1990年以降、バブルの崩壊後の消費低迷と、90年台初頭の大型店舗の積極出店があいまってカテゴリーキラーの出店要請が激増し、その売上規模は拡大し、出店は加速していく。 そして、 駅ビルや駅前百貨店、ビッグチェーンの大型店やショッピングセンターのテナントとして集客に貢献していくのである。 90年代前半、食肉ばかりでなく鮮魚・青果のカテゴリーキラーがメジャーに成長をしていく。 そして、出店場所も、都心部から郊外に進出し始めている。 1992年そのプロトタイプとなった「岡島パワーセンター 後屋店」がオープンする。 売り場面積全体で90坪、月商2億円強。 精肉は三林商事が運営し、月商の平均は初年度5000万を越えた。 カテゴリーキラーは巨大なパワーセンターから、競争に負けたスーパーマーケットの食肉部門へと活躍の場が広がっていく。競合していたスーパーが、カテゴリーキラーを誘致し精肉をテナント化したのだ。 スーパーの売り場活性化の目玉として、各地でカテゴリーキラーの導入が始まる。 スーパーも、自社で精肉を運営するよりは、プロショップを導入するほうが活性化につながり、店舗が生き返る事を実証したのがカテゴリーキラーの存在であった。 その後各地で郊外型パワーセンターが開設され、鮮魚のカテゴリーキラーと共にメジャーと呼ばれるカテゴリーキラー達は出店地を拡大していく。 関西では、1993年「エース新鮮館立花店」が開設され、オーエムツーが出店し、その後ニュークイックが出店し、関西・中国・四国・九州と出店していく足がかりになる。 スーパーが直営の精肉部をもつよりも、販売力のあるカテゴリーキラーを導入する事で、平準化されている競合のスーパーに勝とうというねらいがある。また、レジ部門で金銭勘定を中心に行い生鮮と惣菜はカテゴリーキラーを導入し圧倒的な販売力を競合他社よりも持とう、というのが狙いのスーパーも出現してきた。 |
|
| 「デベロッパーとしても成長」 | |
| 1994年から95年に流通業最大の話題となったのは「カウボーイ」による「上越ウィング」のオープンである。4万5千坪の敷地に1万坪の売り場、90のテナント、1700台の駐車場を有した規模で開設した。 カウボーイは96年に宮城県三本木町、98年にサハリンになど道外に出店し、現在はSCの退店後の店舗に入店し店舗を広げている。 また、温泉施設併設の「恵庭店」を98年開設し、敷地内に「ガーデンゴルフパーク」や「東宝シネコン8」などを併設しレジャー性を高めた施設を開発した。 2000年11月北区新川に巨大な割烹温泉「グルメシップ」をオープンさせ、大型SCの跡地の開発を進めている。 一方九州では、1995年12月8日に3477坪の売り場面積をもつ「ビッグウェイ大宰府」がオープンし、970坪の生鮮食品館を「明治屋産業」がカテゴリーキラーの北辰・九州屋を誘致し「タベルト(TAVELT)」でオープンした。食品スーパーの運営を手がける事になる。 (「タベルト」はその後、精肉テナントとしてだけではなく生鮮を含む食品全体で入店する業態として京都フジイダイマルや、渋谷代官山などに出店をしている。) 「ニュークイック」も「フジガーデン」の店名で鮮魚や青果のカテゴリーキラーを集め食品スーパーを運営している。 |
|
| 「カテゴリーキラー強さの真実」 | |
|
問題は彼らの強さの源泉はどこにあるのか、そして、其れが継続されるのかにある。 |
|
 1980年代から急成長したチェーンの「カテゴリーキラー」とは、スーパーマーケットやGMS、百貨店等の既存の業態が幅広く取り扱っていた商品の分野を専門特化して品揃えをし、価格でさらに競争力をつけた専門店チェーン業態群のことをさす。
1980年代から急成長したチェーンの「カテゴリーキラー」とは、スーパーマーケットやGMS、百貨店等の既存の業態が幅広く取り扱っていた商品の分野を専門特化して品揃えをし、価格でさらに競争力をつけた専門店チェーン業態群のことをさす。
 食肉のカテゴリーキラーは3つに分けられる。1つは、地方で週末の肉の安売りで伸びてきたグループ。もう一つは、駅ビルや百貨店、SC内の出店を図ったグループと、スーパーの精肉テナントとして店舗数を拡大していくグループである。
食肉のカテゴリーキラーは3つに分けられる。1つは、地方で週末の肉の安売りで伸びてきたグループ。もう一つは、駅ビルや百貨店、SC内の出店を図ったグループと、スーパーの精肉テナントとして店舗数を拡大していくグループである。